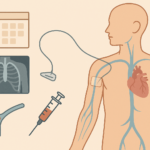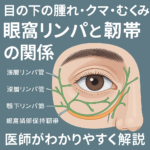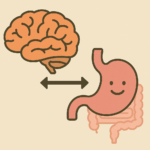RNAシーケンスとは?DNAとの違いと使い分け
こんにちは、今回は「RNAシーケンス(RNA-seq)」について、研究初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
最近では医学研究やバイオの現場でよく使われる技術ですが、「DNAとの違いって?」「何ができるの?」といった疑問も多いはず。今回は実際の鼻茸の研究を例に、RNAシーケンスの基本と活用方法を紹介します。
1. DNAとRNAの違いってなに?
| 項目 | DNA | RNA |
|---|---|---|
| 何か? | 遺伝情報そのもの(設計図) | 遺伝子からコピーされた命令書 |
| イメージ | 図書館にある全ての本 | 今読まれている本 |
| どこにある? | 細胞の核 | 核と細胞質 |
→ DNAは「すべての情報」、RNAは「いま使われている情報」
2. シーケンスとは?
シーケンス=配列を読むこと(遺伝子の文字列を読む)
- DNAシーケンス:どんな遺伝子や変異があるか調べる
- RNAシーケンス:どの遺伝子が使われているか(発現)を調べる
3. DNAとRNAシーケンスの使い分け
| 調べたいこと | 適した方法 | 例 |
|---|---|---|
| 遺伝子に変異があるか? | DNAシーケンス | 遺伝病、がんの原因調査 |
| どの遺伝子が使われているか? | RNAシーケンス | 病気の状態、炎症のタイプ |
| 遺伝子が働かない理由を知りたい | 両方使う | 機能喪失+発現消失の確認 |
DNAシーケンス=設計図チェック、RNAシーケンス=実際の活動チェック
4. 鼻茸の研究にRNAシーケンスを活用
参考論文:Nakayama et al., J Allergy Clin Immunol, 2022
慢性副鼻腔炎(CRSwNP)の鼻茸を対象に、白人と日本人の炎症パターンの違いをRNA-seqで解析しました。
研究の流れ(簡略版)
- 鼻茸組織を採取しRNALaterで保存
- RNA抽出・品質チェック
- ライブラリ作成
- 次世代シーケンス(NovaSeq)
- データ解析(STAR、DESeq2など)
5. 研究でわかったこと
- 白人と日本人で「炎症タイプ(エンドタイプ)」は2つに分かれる(type 2と非type 2)
- 構造は共通だが割合が異なる(白人はtype 2が多い)
- type 2ではCCL13、CST1、CCL18が高発現
- M2マクロファージや上皮細胞が主な発現源(scRNA-seqで確認)
6. まとめ:RNAシーケンスは「いま起きていること」を可視化
- DNAシーケンス=設計図(変異)を調べる
- RNAシーケンス=今どの遺伝子が働いているかを調べる
- 病気の分類や薬の効果判定などに活用できる
- 実際の研究例を知ると、技術の使いどころがわかりやすくなる!
今後も研究初心者の方に向けて、分子生物学の基本と応用をわかりやすく紹介していきます!